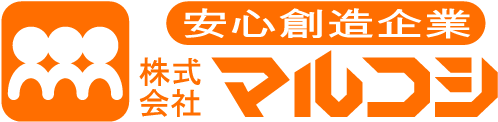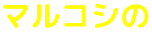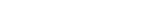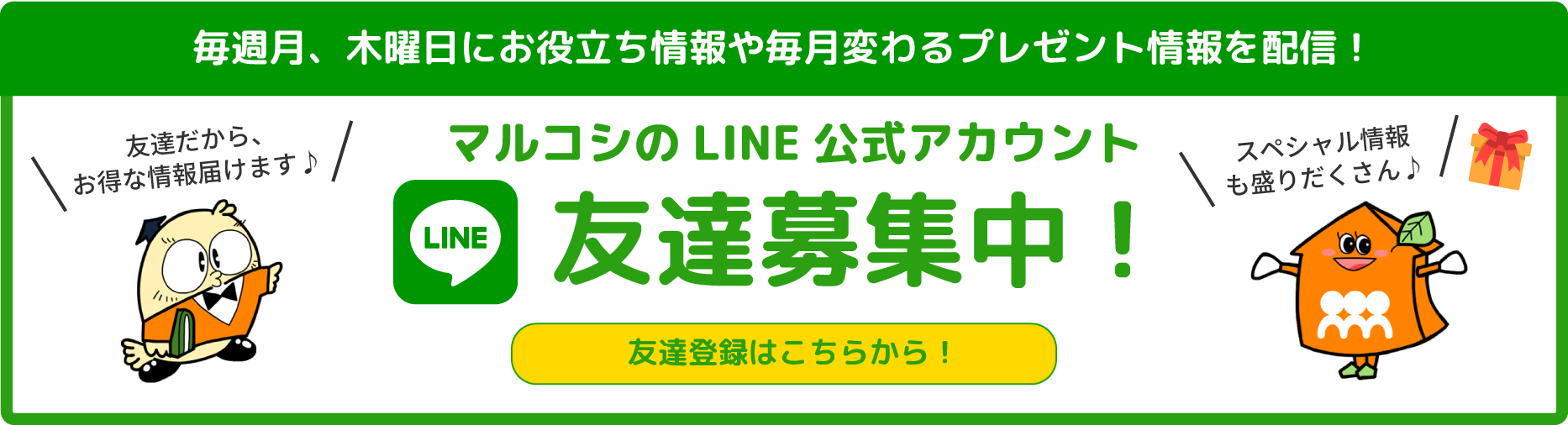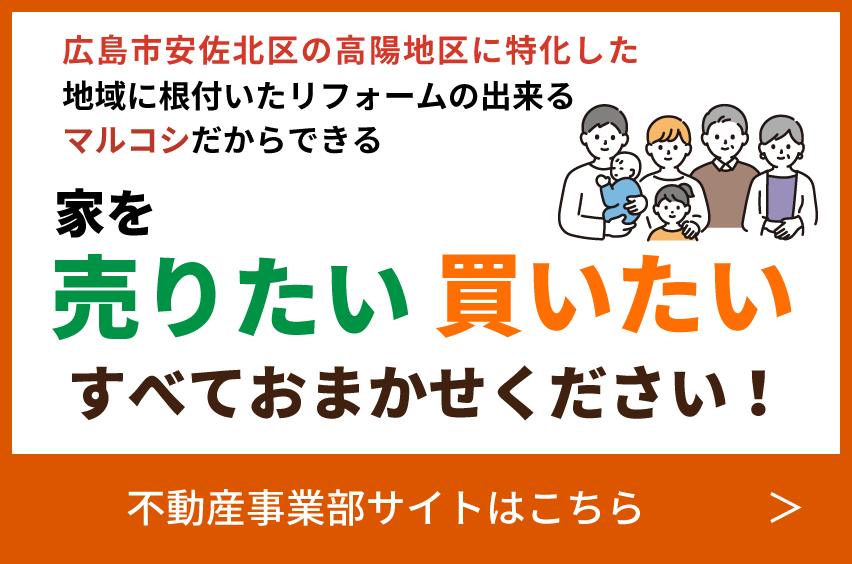平成23年5月13日(No5258) 「震災歌集」の迫力と見識
「震災歌集」の迫力と見識
この『震災和歌集』は2011年3月11午後、東日本一帯を襲った巨大な地震と津波、続いて起こった東京電力の福島第一原子力発電所の事故からはじまった混乱と不安の12日間の記録である。
そのとき私(著者・長谷川櫂)は有楽町駅の山手線ホームにいた。高架のプラットホームは暴れ馬の背中のように振動し、周囲のビルは暴風に揉まれる椰子の木のように軋んだ。
その夜からである。荒々しいリズムで短歌が次々に湧き上がってきたのは。私は俳人だが、なぜ俳句ではなく短歌だったのか、理由はまだよくわからない。「やむにやまれぬ思い」というしかない。
今回の未曾有の天災と原発事故という人災は日本という国のあり方の変革を迫るものだろう。その中でもっとも改めなければならないのは、政治と経済のシステムである。この歌集に出てくるのは菅内閣と東京電力だが、どちらもその象徴に過ぎない。問題は政治と経済全体にある。
地震が起こるずっと以前から今の日本の政治と経済のシステムに漠然とした不安を感じていたのは私だけではないだろう。多くの人々が「このままでいいのか」という疑問をいだいていたはずだ。
決して立派とはいえない首相が何代もつづくのは、間接民主制という政治家を選び出すシステムそのものがすでに老朽化してしまっているからではないか。温暖化など地球という星の存亡が問われながら、電気やガソリンを市場原理のみに任せて湯水のように使い続けていいのか。このひそかな疑問は震災後、切実に日本人一人一人の意識と生活を問い直すことになるだろう。
もしこの問題を棚に上げたまま、もとのように「復旧」されるのであれば、私たちは今回の地震や津波や原発事故から何も学ばなかったことになる。それは今回の大震災でこれほど多くの人が亡くなった、その無残な死を無駄にすることになる。一人の人間の「やむにやまれぬ思い」もそれと無関係ではない。(2011,3,27.)
「東日本大震災」は他人事でないと菅内閣も、東京電力も、識者も、メディアも口を揃えて言う。だが、震災以降の彼らの言動からは「他人事ではない。しかし、自分のことではない」との冷たいメッセージしか伝わってこない。
私は一人でも多くの日本人に、長谷川櫂著『震災歌集』(中央公論新社刊・定価1100円)から迸る熱いメッセージを受け止めて欲しいと願う。政治家と称する人、とりわけ菅直人内閣総理大臣の言い訳を聞かせて欲しい。
|
■津波とは 波かとばかり 思ひしが さにあらず 横ざまにたけりくるふ瀑布 ■乳飲み子を 抱きしめしまま 溺れたる 若き母をみつ 昼のうつつに ■かりそめに 死者二万人となどと いふなかれ 親あり子あり はらからあるを ■おどおどと 首相出て来て おどおどと 何事かいひて 画面より消ゆ ■かかるとき かかる首相を いただきて かかる目に遭う 日本の不幸 ■現地にて 陣頭指揮取る いちにんの 政治家をらぬ 日本の不幸 ■被曝しつつ 放水をせし 自衛官 その名は知らず 記憶にとどめよ ■原子炉の 放射能浴び 放水の 消防士らに掌 合はする老婆
|
(116首のうち 8首を紹介。あとは『震災歌集』でどぞ)